すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について
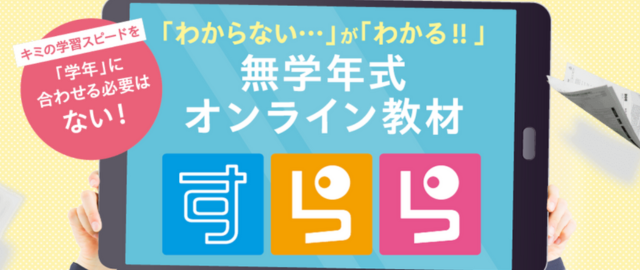
家庭での学習が「学校の出席扱い」になるって、正直ちょっと信じがたい話かもしれません。
でも、すららはそれを実現している数少ない教材のひとつなんです。
不登校の子どもにとって「学校に行けない」という事実は、心にも大きな負担をかけます。
でも、すららを活用すれば、在宅での学習が正式に出席と認められるケースが増えています。
なぜそんなことが可能なのか?その理由は「学習の質」と「記録性」、そして「継続的なサポート体制」が整っているから。
文部科学省のガイドラインに準拠し、教育委員会とも連携している実績があるからこそ、多くの学校がすららの学習を正規の出席としてカウントしてくれるのです。
不登校という選択をした家庭でも、子どもの未来をしっかり支えられる、それがすららの大きな強みです。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららは、ただの家庭学習教材ではありません。
出席扱いが認められる最大の理由は、学習の「質」と「記録性」が非常に高いから。
単元ごとに到達度が記録され、どこを学習し、どのくらい理解しているのかが明確にレポート化されます。
さらに、その学習記録は学校側にそのまま提出できるフォーマットになっており、保護者が手作業で記録をつける必要がありません。
こうした「客観的データのある学習」こそが、教育委員会や学校が出席扱いとして認定しやすい大きな理由です。
すららの記録は「誰でも見える」「手間なく提出できる」「評価されやすい」…この3拍子が揃っているから、安心して在宅学習を進められます。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららには、学習した内容や進捗状況を自動で記録し、レポートとして出力できる機能があります。
このレポートは「いつ」「どの単元を」「どれだけ学習したか」が明確に記録されており、学校側に対して「自宅学習でもきちんと取り組んでいる証拠」として提示できます。
一般的な自習やプリント学習だと証明が難しいですが、すららならその手間を最小限にしつつ、最大限の証明力が得られるのがポイント。
実際、これがきっかけで出席扱いに前向きになった学校もあるほどです。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
多くの保護者が不安に感じるのが「自宅学習の管理」。
でも、すららなら親が毎日付きっきりでチェックする必要はありません。
システムが自動で子どもの学習状況を可視化し、進捗をグラフ化したり、単元ごとの達成度を見せてくれたりします。
そのため、保護者は「見守り」だけでOK。
さらにその情報は学校側にも提出できるため、担任や校長からの評価も得られやすくなります。
「親の負担が少ない」×「学校に伝わる」=安心して使える。
それが、すららの強みです。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
出席扱いが認められるもう一つの大きな理由が、「個別学習の計画性と継続性」です。
すららには「すららコーチ」というプロのサポーターが在籍しており、子どもの性格や学力に合わせてオーダーメイドの学習計画を提案してくれます。
たとえば「午前中は集中力が高いからここに苦手科目を入れる」「一週間に一度はご褒美のある単元にする」など、非常に細やかな設計が可能。
また、コーチから定期的なフィードバックも届くため、子ども自身のやる気にもつながります。
こうした「継続して学べる環境」が整っていることが、教育委員会にも高く評価されているのです。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
すららには、AIだけでなく「人」の力で支える学習設計があることが大きな強みです。
専任のすららコーチは、子どもに合った学習スタイルを見抜き、個別にアドバイスをくれる存在。
学校に提出する際にも「この子はこういう形で継続して学んでいます」という裏付けができるため、説得力が増します。
単なるタブレット学習ではなく、計画と継続がしっかり裏打ちされたシステム。
それが「出席扱いされる教材」として信頼される理由のひとつです。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
すらら最大の強みのひとつが「専任コーチ制度」です。
学習教材でありがちな「やりっぱなし」にならないよう、すららでは担当コーチが一人ひとりの学習状況に合わせて丁寧にサポートをしてくれます。
とくに不登校の子どもは生活リズムが崩れがち。
そんなときにも「この週はここまでやってみよう」と無理のない学習スケジュールを提案してくれるので、親も安心できます。
学習の継続に自信がない子にも、やるべきことが明確になることで前向きに取り組みやすくなります。
「ひとりじゃない」と感じられる環境、それがすららの価値です。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
すららは「無学年式」の教材なので、学年にとらわれず、今の自分に必要な単元に自由にアクセスできます。
不登校になると、学校の授業に遅れを感じたり、逆に退屈になったりすることもありますが、すららならそんな心配は無用。
遅れている教科は小学校範囲に戻って基礎からやり直し、得意な部分はどんどん先取りが可能です。
これにより、無理なく「自分のタイミング」で学べるため、学習のストレスを最小限に抑えることができます。
不登校でも、学力をしっかりキープできる設計がここにあります。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
不登校の出席認定には、「家庭・学校・教材」の三者連携がとても大切です。
すららでは、学校側に必要な提出書類(学習記録など)の準備方法を丁寧に案内してくれます。
また、保護者や学校と連携して動けるよう、専任コーチがフォローに入ってくれる点も安心材料のひとつです。
担任や校長先生との橋渡し役になってくれることもあるので、「どう話を切り出したらいいか分からない…」という保護者の方でも、心強く感じられるはずです。
すららは単なる学習教材ではなく、家庭と学校の架け橋となる存在です。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
学校に出席認定をお願いする際には、「どのような資料を用意すべきか?」という疑問が必ず出てきますよね。
すららでは、こうした疑問にもしっかり対応してくれます。
学習記録の出し方やレポートのフォーマットの準備など、具体的なやり方を説明してくれるので、初めての保護者でもスムーズに対応できます。
申請書類の用意でつまずかないからこそ、学校とのやり取りも前向きに進められるのが嬉しいポイントです。
すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる
すららでは、専任コーチが学習の進捗を定期的にチェックしてくれるだけでなく、学校や教育委員会に提出する学習レポートの書き方までサポートしてくれます。
レポートはただの形式ではなく、「実際に何をどれだけ学んだか」を見える化する大事な資料です。
忙しい親が一人で悩むのではなく、プロと一緒に進められるから、申請の成功率も上がります。
すららのこういった支援体制は、他の教材にはなかなかない強みです。
すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる
学校との連携が苦手だったり、過去にトラブルがあった家庭でも、すららはその間をうまく取り持ってくれる役割を果たします。
「担任や校長にどう伝えたらいいか分からない」「言い方を間違えてこじらせたくない」そんな不安を抱える親御さんも多いはず。
でも大丈夫。
すららのコーチは、これまでに多数の連携事例があるので、どんな風に話を進めたらいいかを一緒に考えてくれます。
保護者だけで背負わないサポート体制が整っているんです。
理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績
すららは、文部科学省のガイドラインに基づき、不登校児の出席扱い教材としての実績を多く持っています。
全国の教育委員会や学校とも連携しており、「すららなら安心」と導入している学校も年々増えています。
単なる教材ではなく、公的な機関がその効果と信頼性を認めているというのは、親にとって大きな安心材料になりますよね。
信頼の証があるからこそ、出席扱いの交渉もしやすく、学校側も前向きに受け入れてくれる可能性が高まります。
すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある
全国の教育委員会や学校で、すららの導入事例は年々増加しています。
不登校の子どもたちに学習の機会を届けるだけでなく、出席認定や補習の代替として活用されるケースも少なくありません。
公立・私立問わず、多くの教育現場で実績があるという事実は、家庭での導入において非常に心強いポイントになります。
すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている
すららは、文科省や自治体からの認定を受けた教材であるため、公式な「不登校支援教材」として学校に紹介できる強みがあります。
ただの家庭学習ツールではなく、制度として出席扱いが目指せる教材だからこそ、信頼されて続けられているのです。
教材選びに悩む保護者にとって、すららのような信頼と実績のある教材は、まさに希望の光です。
理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい
すららは、そのカリキュラムや進捗管理機能、学習内容の構成が「学校教育に準じている」と評価されやすいのが大きな特徴です。
学校の学習指導要領に沿っていて、さらに定期的なレポート出力やフィードバック機能も搭載されているため、「家庭学習であっても、これは立派な授業だ」と学校側が判断しやすいのです。
形式的な学習だけでなく、内容の質が伴っていることで、不登校でも安心して継続できる学習環境が整います。
すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている
すららの学習教材は、国が定めた学習指導要領に準拠して作られているので、学校と同じ水準で学ぶことができます。
そのため、出席扱いを求める際に「この教材で何を学んでいるのか?」という質問にも、明確に答えることができます。
学校の授業と同等の学びを、自宅で実現できるのがすららの魅力のひとつです。
すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある
すららは、単に教材を提供するだけでなく、学習の進捗や理解度に応じたフィードバックも自動で行ってくれます。
この評価システムがあることで、「この子がどこまで理解しているか」「どれくらい頑張っているか」を学校にも示すことができます。
家庭学習でも、しっかりとした学習効果を担保できるという安心感が、学校側からも信頼される理由です。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について
すららは、文部科学省のガイドラインに沿った「出席扱い制度」に対応した教材として、多くの不登校家庭に利用されています。
ただし、出席扱いになるためには、一定の申請手続きと条件を満たす必要があります。
このページでは、すららを使って出席扱いを申請するための具体的な方法をステップごとに解説します。
「何を用意すればいいの?」「どこに相談すればいいの?」と不安に思う方も、ここを読めばしっかり流れが理解できますよ。
初めての方でも安心して申請が進められるよう、できるだけ分かりやすくまとめましたので、ぜひ参考にしてくださいね。
申請方法1・担任・学校に相談する
出席扱いを申請する第一歩は、必ず「学校側との相談」から始めましょう。
具体的には、担任の先生や教頭先生、校長先生に現在の状況を説明し、「出席扱いの申請をしたい」と意思を伝えることが大切です。
文部科学省の通知では、家庭でICT教材を使用した継続的な学習があれば、出席扱いとすることができるとされていますが、実際に承認するのは学校長です。
まずは必要な書類や条件について、学校から具体的に確認をとりましょう。
申請がスムーズに進むかどうかは、ここでの対話がカギになります。
「まだ早いかな?」と迷わず、まずは相談をしてみてください。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
学校に相談した際に、まず確認すべきなのが「どの書類が必要か?」という点です。
通常、必要とされるのは、すららでの学習記録や進捗レポート、家庭での学習支援体制の説明書類、場合によっては医師の診断書などです。
また、学習時間や教科のバランスなど、出席扱いの条件として「学校に準ずる水準の学習」が求められるため、それをどう証明するかも重要です。
提出前に、すららコーチやサポートに相談すると、フォーマットや準備の流れを教えてもらえるので安心ですよ。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
出席扱いの申請においては、不登校の理由によって医師の診断書が求められるケースがあります。
たとえば、精神的な不調や発達障害、体調不良など、医療的な理由で通学が難しい場合は、医師の「診断書」や「意見書」が求められることがほとんどです。
これは、学校や教育委員会が客観的に「この子は通学が難しい状況である」と理解するための重要な資料となります。
提出が必要かどうかは、学校と相談しながら確認しましょう。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
文部科学省のガイドラインにも記載がある通り、「疾病その他やむを得ない理由による場合」は、出席扱いの対象になります。
とはいえ、学校としても「なぜ通学が難しいのか」を確認する必要があるため、医師の診断書が有効な証明書となります。
不登校が長期化している場合や、精神的な不調、発達特性が影響していると感じたら、早めに医師に相談するのがおすすめです。
信頼できる医師に依頼することで、スムーズな申請が可能になります。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書を依頼する際のポイントは、「不登校の状態」だけでなく、「在宅での学習継続が望ましい」という文言も記載してもらうことです。
これにより、家庭学習が単なる選択肢ではなく、子どもの成長と安定にとって必要な手段であることを、学校側にしっかり伝えることができます。
診断書の内容は、申請の可否に大きく影響するため、可能であれば医師と直接相談して、具体的な文面を依頼するようにしましょう。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
出席扱いを認めてもらうためには、「家庭での学習が継続して行われている」ことを具体的に示す必要があります。
すららでは、学習時間・進捗・達成状況などを可視化したレポートをPDFなどでダウンロードすることができます。
これを学校に提出することで、客観的な証拠として認めてもらえる可能性が高まります。
また、すららコーチと相談しながらレポートの書き方を確認したり、必要に応じて補足説明を加えたりすることで、さらに説得力が増します。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららのマイページからは、子どもの学習履歴や進捗状況がグラフ付きでダウンロード可能です。
これをプリントアウトして学校に提出すれば、「何をどれだけ学んでいるか」が明確に伝わります。
担任の先生だけでなく、校長先生にまできちんと共有することで、出席扱いとしての説得力が高まります。
できれば月ごとにまとめて定期的に提出すると良いでしょう。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
最終的な「出席扱い申請書」は、基本的に学校側で作成しますが、保護者のサポートも重要です。
家庭での学習の様子や、子どもの意欲、保護者のサポート体制などを記載する欄がある場合も。
すららでどのように学習しているか、具体的なエピソードを添えて伝えることで、より前向きに検討してもらえる可能性が高まります。
申請書の作成に不安がある場合は、すららコーチにも相談できます。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
書類の提出が完了したら、次は学校長による承認を待つ段階に入ります。
出席扱いとして認めるかどうかは、最終的に学校長の裁量に委ねられているため、これまでのやり取りや提出書類の内容がとても重要になります。
さらに、自治体によっては、教育委員会の承認も必要となる場合があります。
その場合は、学校と連携しながら、教育委員会向けの書類や説明資料を準備しましょう。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
文部科学省の通知によると、「家庭学習での出席扱い」は最終的に学校長が判断します。
そのため、これまでの準備段階でどれだけ丁寧にコミュニケーションを重ね、信頼関係を築けるかが大切です。
すららのように実績のある教材を使い、継続的な学習が行われていることをしっかり示せれば、前向きに承認される可能性は十分にあります。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
地域によっては、出席扱いの判断に教育委員会の承認が必要な場合があります。
このとき、保護者だけで申請を進めるのは難しいため、必ず学校側と連携して進めましょう。
学校が窓口となってくれる場合も多く、すららの進捗レポートや診断書などの資料をそろえて提出します。
教育委員会に対しては、家庭学習の意義や実際の成果を丁寧に説明することで、よりスムーズな承認が期待できます。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します
すららは、文部科学省の出席扱いガイドラインに準拠した教材として、多くの不登校児童・生徒の学習支援に活用されています。
中でも「出席扱い」として認定されることで得られるメリットは、子どもだけでなく保護者にとっても非常に大きいです。
単に学習を続けるだけでなく、学校生活の中での評価や進路にも直結してくるため、早期に正しい手続きを踏んで申請することが大切です。
ここでは、すららを利用して出席扱いとして認められた場合に得られる3つの大きなメリットをご紹介します。
「ただの家庭学習」とは違う、安心と信頼を得られる理由がここにあります。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
中学・高校の進学で重要となるのが「内申点」です。
出席日数が極端に少ないと、成績だけでなく生活態度や意欲の評価にもマイナス影響が出ることがあります。
ですが、すららを通して「出席扱い」が認められれば、出席日数としてカウントされるため、内申点の評価もある程度維持されやすくなります。
学校の先生から見ても「学習を継続している」という事実がはっきりと記録されていることで、安定した評価につながるのです。
これは、将来的に進路の選択肢を広げる意味でも非常に重要。
進学や受験に不利になることを防ぐ大きな一歩になります。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
学校の出席日数が評価に影響するのはよく知られた事実です。
たとえば、中学校で内申点が高校進学に使われる場合、「欠席日数が多い=評価が下がる」ということもあります。
すららを通して継続学習していることが証明されれば、「出席扱い」として出席日数を確保でき、内申点の評価が悪化しにくくなります。
これは本人にとっても大きな安心材料になり、前向きな気持ちで学習を続けるきっかけになります。
中学・高校進学の選択肢が広がる
進学時に「出席日数が少ない」と、それだけで選べる学校が限られてしまうことも。
不登校経験があっても、すららで出席扱いを得られていれば、通常通りの出願や選考が可能なケースも増えてきています。
これは本人の努力が形として残るという意味でも非常に大きいです。
「自分も他の子と同じように進学できるんだ」という自信にもつながり、将来に希望を持てる大きな後押しになります。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校になった子どもが感じやすいのが「もう勉強についていけないかも」という不安です。
しかし、すららは無学年式で、本人のペースで学び直しができるのが大きな強み。
学校での学習と完全に同じ内容ではないものの、教科書準拠で設計されているため、必要な知識はしっかりカバーされています。
加えて出席扱いになることで、学校から「学習している」と認められた安心感も得られます。
これにより、心の焦りや不安が軽減され、学習にも前向きになれるのです。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
すららの特長の一つは「どこからでも学習を始められる」「どこまででも先に進められる」という柔軟性。
無学年式だからこそ、途中でつまずいても、戻って学び直すことが可能です。
逆に得意な分野はどんどん進めることもできるため、「授業の遅れを取り戻せないかも」というプレッシャーから解放されます。
これにより、学習そのものが楽しいものに変わるケースも少なくありません。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
「学校に行けない=ダメな子」と感じてしまう子どもはとても多いです。
ですが、すららのように、家庭で学習しながら成果を実感できる環境があると、「自分にもできることがある」と思えるようになります。
これは自己肯定感の維持や回復に非常に大切な要素です。
さらに、出席扱いとして学校に認められることで「ちゃんと評価されている」という実感にもつながり、自信を持つきっかけになります。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子どもを持つ保護者は、「うちの子は将来どうなるんだろう」「学校に行かないと成績がつかないのでは」と、常に大きな不安を抱えています。
すららを使って出席扱いにしてもらえれば、その不安がかなり軽減されます。
また、すららコーチが学習の進捗や計画をサポートしてくれるので、「毎日勉強を見てあげないと…」というプレッシャーも減り、親子関係がギスギスしにくくなるという副次的な効果も。
家族全体にとって、大きな心の支えになるのがこの制度です。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららには「専任コーチ」という強力な味方がいます。
保護者とだけでなく、学校とも連携できるよう資料の準備を手伝ってくれたり、レポートの出力やアドバイスもしてくれるため、保護者が1人で対応に追われることはありません。
学校とのコミュニケーションが不安な場合も、コーチのサポートがあることで気持ちがラクになります。
「一緒に見守ってくれる人がいる」という安心感は、親にとって本当に心強い存在です。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します
すららを使って「出席扱い」にしてもらうには、ただ学習を続けるだけではなく、学校との連携や適切な書類の準備が必要になります。
文部科学省が出しているガイドラインに基づいて学校側が判断するため、事前準備をしっかり行っておくことが成功のカギです。
また、保護者と学校だけでなく、医師やコーチなど第三者の協力も重要になる場合があります。
ここでは、すららで出席扱いを受けるために気をつけたい具体的な注意点を紹介します。
焦らず、丁寧に一つずつ進めていくことで、安心して自宅学習を継続しながら、学校との信頼関係も築いていくことができます。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
すららで学習をしていても、それが「出席扱い」として認められるかどうかは、学校側の判断に委ねられます。
つまり、いくら頑張って学習をしていても、担任や校長先生が「家庭での学習を出席として認めます」と明確に判断してくれなければ、カウントされないのです。
そのため、すららの教材が「文部科学省のガイドラインに沿った学習支援教材」であることをきちんと説明する必要があります。
口頭ではなく、資料やパンフレットを見せながら、客観的に伝えるのがポイント。
学校側の不安を取り除き、「協力していきたい」と思ってもらうことが何よりも大切です。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
すららは、文部科学省の「不登校児童生徒の出席扱いに関するガイドライン」に則った教材です。
しかし、すべての学校や先生がその情報を持っているとは限りません。
そのため、保護者からの説明が重要になります。
「すららは教育機関でも使われているオンライン教材で、文科省の基準にも合っています」と具体的に伝えましょう。
また、公式サイトからPDFなどの資料を印刷して持参すれば、先生も内容を理解しやすく、納得しやすくなります。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
出席扱いは、担任だけでなく校長先生の承認が必要になることが多いため、できるだけ早めに学校の中でも影響力のある立場の先生方に相談しておくことが大切です。
「担任に伝えておけばOK」と思い込まず、教頭先生や学年主任にも共有しておくとスムーズです。
さらに、すららが発行するレポート例や資料を一緒に見せれば、「具体的にどんな学習をしているのか」が明確に伝わります。
情報はなるべく視覚的に伝えるのがポイントです。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
出席扱いを申請する際、不登校の理由によっては医師の診断書や意見書が求められることがあります。
特に、精神的な理由や慢性的な体調不良が原因で学校に通えていない場合は、学校が「医学的な裏付け」を求めるケースが多いのです。
そういった場合は、早めに小児科や心療内科を受診し、医師に現在の状況を伝えた上で診断書を発行してもらいましょう。
診断書は単なる書類ではなく、「第三者の視点による証明」として学校側への大きな説得力になります。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
学校側としては、「なぜ通えていないのか」「それでも学習は続けられる状態なのか」を把握した上で判断したいという考えがあります。
そのため、家庭内の説明だけでは不十分で、医師からの意見書が求められることがあります。
具体的には、「不安障害」「起立性調節障害」「うつ症状」などの診断がされていれば、それに基づいて「家庭学習を推奨する」といった内容を含めてもらうのが望ましいです。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書や意見書は、医師に対してただ「診断書ください」と言うだけではなく、用途を明確に伝えることが大切です。
具体的には、「学校に出席扱いとして認めてもらうために必要な診断書がほしい」と説明しましょう。
そうすることで、医師もどのような内容を書けば良いのかが明確になり、必要な文言を入れてくれる可能性が高まります。
曖昧なまま依頼してしまうと、後から書き直しをお願いする手間が発生することもあるので注意です。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
診断書を発行してもらう際、医師が書く内容は診察時の様子やヒアリングに基づくため、保護者側からの情報提供も重要です。
「自宅でオンライン学習を継続している」「本人に学習意欲がある」など、具体的な状況を共有することで、より前向きな記載につながります。
たとえば、「家庭での学習状況は良好で、継続的な学習が望ましい」などと書かれていると、学校側への印象も良くなり、出席扱いが認められやすくなります。
注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いとして認めてもらうためには、学習時間や内容が「学校で行われている授業と同等である」と学校側が判断できるレベルである必要があります。
ただ「タブレットで自習している」だけでは難しく、学習内容が文部科学省の学習指導要領に基づいていること、主要教科を含めてバランスよく学習していることが求められます。
また、毎日の学習時間もポイントになります。
たとえば1日30分だけの学習では、どうしても「学習継続性がない」と判断されてしまう可能性があるため、1日2〜3時間程度を目安にコツコツ取り組むことが大切です。
すららでは、学習履歴が自動で記録され、進捗も見える化されるので、こういった条件をクリアしやすいのが強みでもあります。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
たとえば、市販の問題集をただ解くだけでは「単なる自習」とみなされ、学校の授業に準ずるとは言えません。
一方、すららのように、文科省の学習指導要領に準拠した教材であれば、学校側から「学校の授業に準じた学びをしている」と認識してもらいやすくなります。
動画授業や確認テスト、定期的なレポートなど、学習の中身がしっかりしていることが大切。
出席扱いを希望するなら、そうした質の高い教材を選びましょう。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
学習の時間も、非常に重要な要素です。
出席扱いの判断には、「継続性」と「時間的なボリューム」が見られます。
理想は学校と同等の時間、つまり1日5〜6時間ですが、それが難しい場合でも2〜3時間の集中した学習を継続することで、十分に評価対象になります。
すららの学習設計は、短時間で区切りをつけやすく、集中力が途切れやすい子にも向いています。
家庭のスケジュールと無理なく組み合わせることで、習慣化も図りやすくなります。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
出席扱いが認められるかどうかの基準のひとつに、「学習の網羅性」があります。
つまり、国語・数学・英語だけでなく、理科や社会など、学校で教えられている教科すべてにバランスよく取り組んでいるかが見られます。
すららは、3教科〜5教科のコースがあり、必要に応じて選択・拡張が可能。
教科に偏りが出てしまっている場合は、出席扱いが難しくなることもあるので、相談しながら5教科のバランスを意識しておくと安心です。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いは、「学校との信頼関係」があって初めて成立する制度です。
つまり、家庭側が一方的に学習しているだけではなく、その様子を学校側としっかり共有し、「本当に学んでいるんだ」という証拠と安心感を定期的に届ける必要があります。
すららは、学習記録やレポートを自動で出力できる機能があるため、それを月1回提出するだけでも大きな信頼につながります。
担任の先生とのやりとりも、月1回のメールや電話での報告を意識しておくと良いでしょう。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
どれだけ家庭学習をしていても、学校側がその状況を把握していなければ出席扱いにはできません。
そのため、定期的に学校へ「家庭での学習記録」や「学習の様子」を共有する必要があります。
報告方法としては、メールや印刷して持参、面談などが考えられます。
すららを活用していれば、進捗レポートをPDFで簡単に出力できるので、提出もスムーズです。
提出を「習慣化」することで、学校との信頼関係も築かれていきます。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
「どれだけ勉強しているか」は主観的なものではなく、客観的な記録として提出するのが基本です。
すららでは、毎月の学習時間・単元・進捗状況を自動で可視化した「学習レポート」が出力可能です。
このレポートを月に1回、担任または教頭に提出することで、学校側も「きちんと家庭学習が行われている」と納得しやすくなります。
印刷して提出、PDFでメール送付、どちらでも対応できますので、自分のスタイルに合った方法で提出を継続していきましょう。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
中には、学校側が「直接様子を見たい」と家庭訪問や面談を希望するケースもあります。
突然の連絡に驚くこともあるかもしれませんが、拒否するのではなく、柔軟に対応する姿勢を見せることが大切です。
家庭での学習環境を見てもらったり、子どもが実際に学んでいる様子を説明することで、より安心して「出席扱い」を判断してもらえます。
あくまで協力体制を築くことがゴールなので、オープンな姿勢を持ちましょう。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
定期的に学習レポートを提出するだけでなく、担任の先生と日常的に連絡を取り合うことも出席扱いにおいては非常に効果的です。
たとえば、「最近は〇〇の単元に取り組んでいます」「先日、レポートの中でつまずいていた部分が解決しました」といった簡単な報告だけでも、先生にとっては「ちゃんと頑張ってるんだな」と伝わります。
連絡手段は、電話・メール・LINE(許可があれば)など、自分たちが無理なく続けられる方法でOKです。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
すららでの学習を出席扱いとして認めてもらうためには、場合によっては教育委員会への申請が必要になることもあります。
とくに、私立ではなく公立の学校に通っていて、なおかつ校長の判断だけでは足りない自治体の場合、学校と教育委員会が協力して判断を下すケースがあります。
その際は、学校側から「このケースは教育委員会への申請が必要」とアナウンスされるので、保護者としてはその流れに沿って資料を準備し、粘り強く対応していくことが大切です。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会へ申請する場合、すららの学習記録だけでなく、医師の意見書や家庭でのサポート体制、学習環境の写真など、複数の資料が求められることもあります。
そのため、すべてを保護者一人で進めようとせず、学校と連携を取りながら段階的に準備していくことがポイントです。
すららのサポートチームやコーチからも資料やテンプレートを提供してもらえるので、必要なときは遠慮せず頼るようにしましょう。
「孤軍奮闘」にならないことが成功のカギです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します
すららでの学習を「学校の出席扱い」として認めてもらうには、ただタブレット学習を進めるだけでは不十分です。
文部科学省がガイドラインを設けているとはいえ、最終的には各学校・教育委員会の判断によります。
そのため、家庭と学校が連携しながら「学習の質」「本人の学ぶ意思」「継続性」をしっかりと伝えることが成功のカギになります。
すららは、こうした申請に必要な「客観的な証明」「学習レポート」「個別支援」が整っており、不登校支援教材として多くの実績があります。
成功する家庭には、いくつかの共通ポイントがあるため、今回はその「成功パターン」をしっかり紹介します。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
出席扱いにしてもらえるかどうかは、学校側の理解と安心感が非常に大切です。
すららを使って出席扱いになった事例は全国で増えてきており、公式サイトでもその実績が掲載されています。
「他校ではこういう前例があります」と具体的に提示できると、学校側も判断しやすくなります。
特に、同じ市区町村・都道府県内の学校で実績がある場合、その事例をプリントアウトして持参し、校長先生や担任に説明すると説得力が格段に上がります。
「うちの子だけ特例なのでは?」という不安を減らすことが、成功の第一歩です。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
保護者が一番苦労するのが「説得材料」です。
そこで活用したいのが、すららの出席扱い実績一覧です。
「◯◯市立△△中学校でも、すららを使って出席扱いになった」といった具体的な事例は、学校側にとって非常に心強い判断材料になります。
事例を示すことで「これは特別なケースではない」「制度として成り立っている」という印象を与えられるため、申請時に有利になります。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
すららの公式ページには、出席扱いが認められた学校の一覧や活用事例が掲載されています。
それを事前に確認し、PDFやスクリーンショットをプリントして学校へ持参するのがおすすめです。
目に見える資料をもとに話すことで、校長先生や教育委員会の担当者も納得しやすくなります。
たとえ説明が苦手でも、資料の力で後押しができますよ。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
出席扱いの制度では、家庭や学校の努力だけでなく「本人の意思」が重視されます。
つまり、「親がやらせているのではなく、自分の意思で学んでいる」と学校側に伝えることが必要不可欠です。
本人が書いた学習の感想や目標、学習計画への意見など、どんなに小さなことでも本人の言葉があると、教育委員会や担任の受け取り方が大きく変わります。
可能であれば面談にも参加して、自分の気持ちを伝えることが、出席扱いに向けた最大の説得材料になります。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
「自分はなぜ勉強をしているのか」「今、どこまで頑張っているのか」「どんなことが楽しいのか」——本人の言葉でこうした気持ちを短いメモでいいので書き出して提出すると、それだけで学校側の印象はぐっと変わります。
作文でなくても、箇条書きやイラスト入りでもOK。
本人が「学ぶ意志」を持っていることが伝われば大丈夫です。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
出席扱いの判断を左右するのが、実は「本人の様子」です。
もし面談や訪問指導の機会があるなら、子ども自身にも参加してもらいましょう。
完璧な受け答えをする必要はなく、「毎日ちょっとずつやってます」「すららで理科をがんばってる」といった一言だけでも、学校側にしっかりと伝わります。
無理のない範囲で、本人の声を届けることがポイントです。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
どれだけ熱意があっても、続かなければ出席扱いにはつながりません。
継続できる現実的な学習計画を立てることが何より重要です。
ここで大活躍するのが「すららコーチ」の存在。
子どもの特性やスケジュール、気分の波に合わせて無理のないペースで学習計画を組んでくれます。
「がんばらせる」よりも、「自然に続けられる」設計が、制度を通すためには必要です。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
毎日4時間頑張る!と意気込んでも、1週間で続かなくなるようでは意味がありません。
本人のペース、生活リズム、気分の変動に合わせて、「1日30分から」など現実的なスタートラインを設定することが、制度を通す上でのポイントです。
継続している実績こそが、学校や教育委員会への最大の説得力になります。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららには専任の学習コーチが付きます。
保護者が無理にスケジュールを組まなくても、コーチが子どもの性格・得意・不得意に合わせて、無理なく続けられるスケジュールを提案してくれます。
こうして「プロによる設計」があることも、出席扱いの信頼材料として強力に働きます。
迷ったら、コーチにどんどん相談しましょう。
ポイント4・:「すららコーチ」をフル活用する
出席扱いを勝ち取るための「資料作成」「学習進捗の証明」「報告書の提出」など、保護者の負担は決して小さくありません。
そんなとき、すららのコーチは最大の味方になってくれます。
進捗管理やレポートのダウンロード方法など、細かな部分までサポートしてくれるので、安心して任せられます。
困ったら、ひとりで抱え込まず、まずはコーチに相談するのが成功の近道です。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
コーチに相談すれば、どのタイミングでどの資料を出すべきか、どうすれば学校側に伝わりやすいかなど、具体的なアドバイスを受けることができます。
また、すららのシステムを通じて自動で作成される学習レポートを、学校向けにどのように加工・説明すれば良いかも相談可能です。
出席扱いは、コーチと家庭が連携して進めるチーム戦。
遠慮せず、どんどん頼ってください。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。
でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。
時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。
イライラして何度も怒ってしまっていましたが、
すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。
完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。
タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。
キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。
教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。
他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
「すららはうざい」という口コミの背景には、主に「サポートが手厚すぎる」「連絡が多い」といった理由があるようです。
実際、すららは学習の継続を目的として、コーチからのメールや電話サポートを積極的に行っています。
そのため、「自分のペースでやりたい」「干渉されたくない」と感じる一部の子どもや保護者には、逆にストレスになることも。
また、キャラクターの演出や、アニメによる対話型授業が「子どもっぽい」「くどい」と感じる高学年の子もいます。
とはいえ、多くの利用者からは「継続につながった」「安心できるサポートだった」といった前向きな評価が多いのも事実。
お子さんのタイプに合わせて、合うかどうか判断するのが良いでしょう。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには「発達障害専用コース」はありませんが、発達障害のお子さんに配慮した機能やサポート体制が整っており、通常のコース内で対応しています。
料金は、学年や教科数に応じて変動し、例えば「小中コース3教科」は月額8,800円、「5教科コース」は月額10,978円が目安です。
発達障害があっても、割引制度は基本的にはなく、全ての子どもに対して「公平な料金設定」をしている点が特徴です。
代わりに、合理的配慮として、学習時間を短く設計したり、音声・アニメーションで理解を促したり、学習計画の個別設計を提供してくれる点が強みです。
療育手帳の有無に関係なく、全ての子どもに「個別最適化された学習」が提供されます。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
はい、すららは文部科学省の「出席扱いのガイドライン」に沿って作られた教材の一つであり、不登校の子どもが家庭で学習した内容を出席扱いにしてもらえる可能性があります。
出席扱いのためには、主に①学習の質と記録、②個別最適な学習計画、③学校・家庭・教材の三者連携、④学校長・教育委員会の承認、など複数の条件が必要です。
すららは、学習の進捗記録やコーチのサポートが整っているため、こうした制度利用に適しています。
また、実際にすららを活用して出席扱いとなった家庭も全国に多く、公式サイトにもその事例が紹介されています。
ただし、学校や地域によって申請方法は異なるため、早めに学校と相談を始めましょう。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららには入会金が無料になるキャンペーンコードが不定期で配布されており、特定の方法で入手したうえで入会時に入力することで、割引が適用されます。
主な入手方法は「資料請求後の説明会参加」や「株主優待」、「兄弟紹介キャンペーン」などです。
使い方は非常に簡単で、申込フォームにキャンペーンコードを入力するだけでOK。
コードが適用されると、通常7,700〜11,000円かかる入会金が無料になったり、月額料金が一定期間割引になることもあります。
注意点として、キャンペーンには有効期限があることや、対象コースが限定されていることもあるため、事前に確認しておきましょう。
再入会時には適用外になるケースもあるためご注意を。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららを退会するには、「解約」と「退会」の2ステップがあることに注意が必要です。
まずは解約申請を行い、月額料金の支払いを停止する必要があります。
解約はマイページから「お問い合わせフォーム」を通じて申請します。
毎月25日までの申請で翌月から料金が発生しません。
次に、完全に退会したい場合は「退会申請」を別途行い、アカウント情報や学習データの削除を依頼します。
解約だけではデータが残り、再開時に入会金がかかりませんが、退会すると再登録が必要になります。
退会前に「再開の可能性があるかどうか」を慎重に考えてから手続きを進めましょう。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららは基本的に「入会金」と「月額受講料」のみで利用でき、追加教材費や更新費などは一切かかりません。
教材はすべてタブレットやPC上で提供されるため、紙のテキスト代や教材発送に関する費用も不要です。
もちろん、タブレット端末をお持ちでない場合は別途準備が必要ですが、すらら専用端末の購入は不要で、市販のもの(推奨スペック内)であればOKです。
また、兄弟で利用する場合なども、アカウントを分ける限り追加費用が発生するケースもあります。
ですが、基本的にはとてもシンプルな料金体系になっているため、「始めてみたら追加料金があって焦った…」ということは起きにくいのが安心ポイントです。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららでは、1つの契約で複数人のアカウントを同時利用することはできません。
つまり、兄弟それぞれが学習するには、1人分ずつ契約が必要です。
ただし、2人目以降の入会金が無料になる「兄弟紹介キャンペーン」があるため、最初の入会者が契約中であれば、2人目以降は少しお得に始めることができます。
また、家族で利用する際には、同じメールアドレスで複数アカウントを管理することも可能なので、保護者の負担は少なく済みます。
タブレットやPCを共有しても問題なく、ログイン情報を切り替えることで、それぞれの進捗を個別に管理できますよ。
「兄弟でお得に始めたい!」という方には、紹介制度の活用が非常におすすめです。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースには「英語」も含まれています。
対象となるのは「3教科コース(国・算・英)」または「5教科コース(国・算・理・社・英)」で、英語はそのうちの1教科として組み込まれています。
内容としては、英単語の発音練習から、リスニング・リーディング・スピーキングまで幅広く対応しており、音声機能付きでネイティブ発音がしっかり身につく設計になっています。
英検5級〜3級レベルまでを想定した基礎力の育成に力を入れており、小学生のうちから「英語に慣れさせたい」という保護者の方に人気があります。
また、アニメーションや音声を使って楽しく学べるため、飽きずに続けられるのも魅力です。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららの最大の特徴のひとつが、「すららコーチ」によるきめ細やかなサポート体制です。
入会時にお子さまの学習状況や特性に合わせて学習計画を一緒に立ててくれるのはもちろん、定期的な進捗チェック・アドバイスも行ってくれます。
たとえば「最近学習ペースが落ちている」「苦手単元が出てきた」といった場合には、個別に連絡があり、学習プランの見直しやモチベーションのサポートが受けられます。
また、保護者からの相談にも丁寧に応じてくれるため、「どう声かけしたらいい?」「子どもの特性に合う学習の進め方は?」といった悩みにも専門的な視点でアドバイスしてくれます。
学習だけでなく、子育ての伴走者としても心強い存在です。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました
すららは「文部科学省のガイドラインに沿った不登校対応教材」として、家庭での学習を学校の出席扱いにできる数少ないタブレット教材のひとつです。
他の家庭用タブレット教材と比べても、学習記録の保存・レポート作成・学校との連携支援などが非常に手厚く、実際に全国の教育委員会や学校で導入実績があります。
一方で、一般的な家庭学習教材は「家庭学習用」として設計されており、出席扱いに必要な条件(学習の継続性・内容の適正・報告体制など)を満たせないことが多いです。
すららはこれらのハードルをシステム的にクリアしており、保護者が安心して申請できる環境が整っています。
不登校児童の学習保障だけでなく、「内申点の維持」「進学の準備」にもつながる点で、他社教材より明確に優位性があります。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ
すららを利用して出席扱いを認定してもらうには、文部科学省が定めた「出席扱い制度」に基づいて、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、学校側に相談し、家庭での学習内容が「学校教育に準ずる内容」であることを説明します。
すららは学習指導要領に準拠した教材であるため、この点で安心です。
次に、学習の記録(レポート)や医師の意見書(必要な場合)を準備し、学校または教育委員会に提出します。
申請が受理されれば、すららでの学習が「出席日数」としてカウントされます。
ただし、出席扱いの判断は最終的に「学校長の裁量」によるため、信頼関係を築きながら丁寧な説明が不可欠です。
また、申請後も定期的な進捗共有が必要となるので、親子で計画的に準備することが成功のポイントです。
